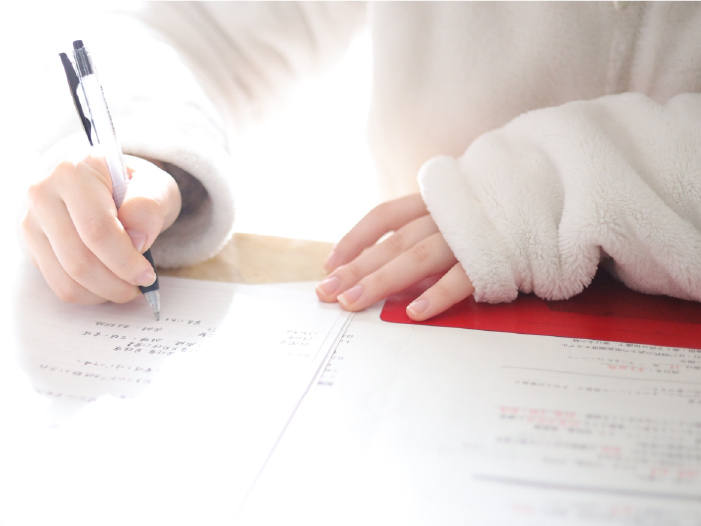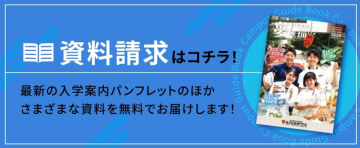Toyo Medical College
外国人傷病者への対応とは?救急隊の医療行為を徹底解説!
2025.09.18

近年、日本を訪れる外国人旅行者や在住外国人は増加の一途を辿っており2019年には年間3,000万人を超える外国人が来日しました。
新型コロナウイルスの影響で一時的に減少したものの、国際的な往来の再開により、再び訪日外国人の数は増え続けています。
こうした中、観光地や都市部、空港などで外国人が急病や事故に遭い、救急要請を行うケースも増加しています。
これにより、救急隊は「言語の壁」や「医療制度の違い」といった課題に直面しながらも、迅速かつ的確な対応が求められるようになっています。
今回は救急隊が外国人傷病者の方に、どのようにコミュニケーションを取り、医療行為を行っているかご紹介します。
救急隊の現在の対応
1.言語の課題と対策
外国人傷病者への対応で最も大きな課題の一つが「言語の壁」です。救急現場では、
①痛みの箇所
②持病やアレルギーの有無
③現在服用中の薬
などの医療情報を正確に聞き出す必要がありますが、言葉が通じないことでスムーズな情報収集が困難になる場合があります。
この課題に対応するため、多くの消防本部では以下のような多言語支援ツールを導入しています 。
①電話による多言語通訳サービス
②多言語会話シート(指差しシート)
③専用の音声翻訳アプリ(後述)
2.病院の選定
外国語対応可能な病院は全国に均等に存在しているわけではありません。
特に地方部では、医療機関での通訳体制が十分でないこともあり、救急搬送先の選定が課題となります。
そのため、多くの消防本部では外国人診療に積極的な医療機関のリストを整備し、適切な搬送先を迅速に選定できる体制を構築しています。
3.医療費への不安
在住外国人の中には、保険未加入者や保険証を提示できない人もいます。
そのため、現場で費用に関する不安を口にするケースも見られます。
救急隊員は医療費請求に直接関与することはありませんが、傷病者の不安に寄り添い、安心感を与えることも重要な役割です。
4. 地域社会との連携
ホテル、観光案内所、空港などの職員と連携し、地域全体で外国人への医療支援体制を整えることが求められます。
救急対応は医療機関だけでなく、地域全体の協力体制がカギとなります。
音声翻訳アプリ「救急ボイストラ」とは?
「救急ボイストラ」は、情報通信研究機構(NICT)の音声翻訳アプリ「VoiceTra(ボイストラ)」を基に、消防庁消防研究センターが救急現場向けに開発した多言語音声翻訳アプリです。
参考文献:防災科学技術研究所一般財団法人消防防災科学センター |
主な特徴
■救急用定型文(46フレーズ)をワンタッチで翻訳・音声再生
■15言語対応(英語、中国語、韓国語、スペイン語、フランス語など)
■音声+テキストによる表示で、聴覚障害者との対応にも有効
■無料で利用可能(通信費のみ自己負担)
導入の背景
訪日・在住外国人の増加と共に、救急現場での対応時間の長期化が課題となっていました。
これに対応するため、「情報難民ゼロプロジェクト」の一環として本アプリが開発されました。
参考文献:防災科学技術研究所
導入状況(2025年時点)
■全国720消防本部中、690本部(約95.8%)が導入
■高い普及率を誇り、現場での通訳時間の短縮や対応の円滑化に大きく貢献
今後の取り組み
1.救急隊員の語学力向上
英語だけでなく、中国語や韓国語など、話せると役に立つ言語の基礎フレーズを覚えておくことも大切です。
問診や処置の説明などで、ほんの少しでも聞き取れたり指示が伝えられたりするだけで、現場の混乱をぐっと減らすことができます。
2.ICTの活用
■AI翻訳アプリやタブレット端末によるリアルタイム翻訳
■外国人向けの救急医療ガイドや予防情報の多言語提供
こうしたICTの活用により、救急隊と外国人とのコミュニケーション精度が向上します。
おわりに
外国人傷病者への救急対応は、単なる「言葉の壁」を超え、医療制度、文化、保険制度など、さまざまな側面を含む複雑な課題です。
しかし、これは同時に、日本の救急医療がより柔軟で国際的な対応力を持つチャンスになるかもしれません。
今後さらに、救急隊員の語学力向上やICTの導入・進化が進むことで、日本人だけでなく、外国人も安心して救急医療を受けられる社会の実現が期待されます。
東洋医療専門学校では上記を考慮し、英会話の授業に加え医療英語といった科目やICTに関する授業を組み込むことで国際教育に注力しています。
ぜひ東洋医療専門学校で救急救命士の国家資格取得を目指してみませんか?
救急救命士・医療従事者としての知識を外国人傷病者の方にも活かしてください。