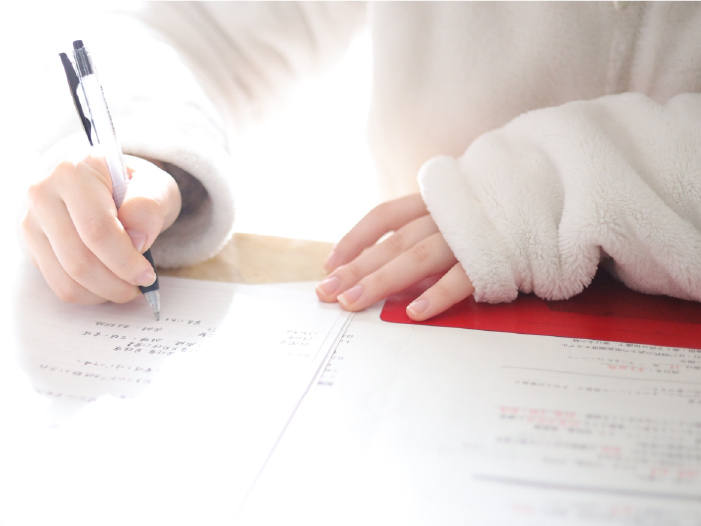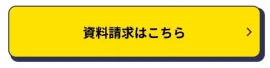Toyo Medical College
自律神経を整えよう 〜鍼灸の視点から考える心と体のバランス〜

「最近なんとなく疲れが取れない」「夜なかなか眠れない」「理由もなくイライラしてしまう」――。
こうした症状の背景には、自律神経の乱れが隠れていることが少なくありません。
自律神経は、私たちの意思に関わらず体の働きをコントロールする重要な仕組みです。
活動時に働く「交感神経」と、リラックス時に働く「副交感神経」がバランスを取りながら心身を調整しています。
しかし、ストレスや不規則な生活、過度なスマホ使用などでこのバランスが崩れると、心身にさまざまな不調が現れます。
そこで注目したいのが、古くから心身を整える手段として活用されてきた鍼灸(しんきゅう)です。
鍼やお灸は単なる痛みのケアにとどまらず、自律神経の働きを整えるサポートとしても有効とされています。
鍼灸から見た自律神経の乱れ
東洋医学では、体を「気・血・水」の流れで捉えます。
ストレスや疲労で気の流れが滞ると、体のバランスが崩れ、
不眠や倦怠感といった症状が現れやすくなると考えられています。
そういった背景がある中で、鍼灸の刺激が血流を改善し、神経伝達物質の分泌を調整することによって、
自律神経に作用することが研究で明らかになっています。
特に施術を通して、副交感神経を優位にしてリラックス状態を作りやすいとされ、
慢性的なストレスや不眠で悩む方に効果が期待できます。
自律神経に働きかける代表的なツボ
鍼灸師の現場では、自律神経の乱れに対して以下のようなツボがよく用いられます。
①百会(ひゃくえ):頭頂部にあるツボ。心身をリラックスさせ、不眠や自律神経失調に効果的とされます。

②内関(ないかん):手首の内側にあるツボ。
ストレスや不安感、動悸に有効といわれています。

③足三里(あしさんり):膝の下にあるツボ。
全身の気を整える代表的なツボで、疲労回復や消化器系の不調にも役立ちます。

④神門(しんもん):手首の小指側にあるツボ。
心を落ち着け、安眠を促す効果が期待されます。

これらはセルフケアとして指で優しく押すだけでも効果がありますが、
プロの鍼灸師が行う施術では、体全体の状態を診ながら的確にツボを選び、鍼やお灸でより深く働きかけます。
日常生活でできる自律神経ケア × 鍼灸の活用
自律神経を整えるには、日々の生活習慣と鍼灸を組み合わせることが効果的です。
呼吸法:腹式呼吸で副交感神経を高める。
睡眠リズムの安定:就寝前のスマホを避け、眠りやすい環境を整える。
適度な運動:ウォーキングやヨガで血流を促進。
食事:発酵食品やビタミン・ミネラルを意識的に摂取。
こうしたセルフケアに加えて、定期的に鍼灸を受けることで心身のリセット効果が期待できます。
特に、肩や首のコリは交感神経を刺激しやすいため、鍼灸で筋肉をゆるめることが自律神経の安定につながります。
鍼灸師からのアドバイス
「自律神経が乱れているのでは?」と感じるとき、多くの方は病院に行くほどではないと考えて我慢しがちです。
しかし、その小さな不調を放置すると慢性化してしまうこともあります。
鍼灸は副作用が少なく、体質や症状に合わせて柔軟にアプローチできるのが大きな魅力です。
もし慢性的な疲れや不眠、原因不明の体調不良で悩んでいるなら、一度施術を受けてみるのも良い選択肢でしょう。
まとめ
自律神経のバランスは、心身の健康に直結します。
深い呼吸や規則正しい生活、適度な運動といったセルフケアはもちろん大切ですが、そこに鍼灸の力を取り入れることで、より確かな整え方が可能になります。
自分の体に耳を傾け、無理のない範囲で整える習慣を積み重ねること。
それが、現代社会でストレスに負けない健やかな心と体を保つ秘訣といえるでしょう。
「鍼灸師」というお仕事に興味を持たれた方は、ぜひこちらからチェックしてみてくださいね!
▶東洋医療専門学校の鍼灸師学科についてはこちら