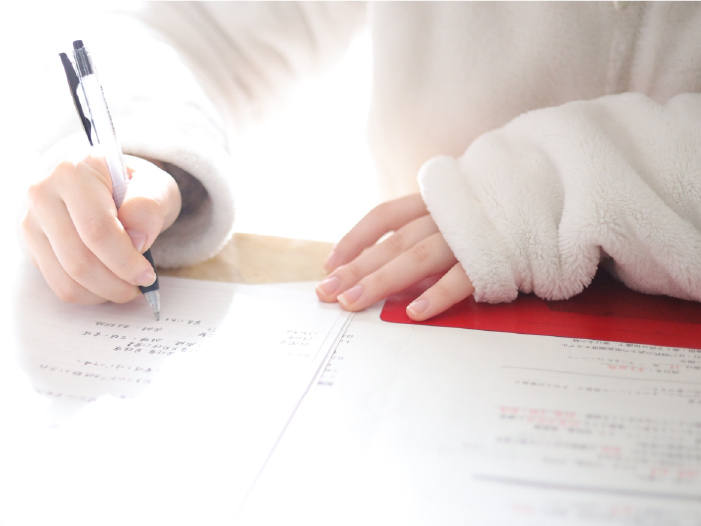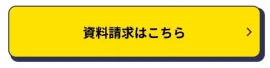Toyo Medical College
歯科技工士国家試験の実技科目について詳しくご紹介
歯科技工士は、人間にとって非常に重要な「歯」に関わる仕事です。
この記事では、まずは歯科技工士の基礎的な知識を紹介したうえで、歯科技工士になるために必要な国家試験で実施される実技試験について解説していきます。
目次
国家資格である歯科技工士は、2つの試験から成る
まず初めに、「そもそも歯科技工士とはどんな仕事か」「資格を取るための方法」「試験の内容と合格率」について簡単に解説していきます。
歯科技工士とは、歯の詰め物、入れ歯、かぶせ物、矯正装置などを作る仕事です。
また、これらの修理や加工なども含めて歯科医師・歯科衛生士と連携し、患者さんが満足できるような歯科技工物を作製します。
歯科技工士は医療系の国家資格のうちの一つであり、専門の養成機関(専門学校の2年制または3年制・大学4年制)に通わなければ受験資格を得ることができない資格です。
通信教育のみでは、受験資格を得ることはできません。
歯科技工士の資格試験は、学科試験(学説試験)と 実技試験(実地試験)の2つから成ります。
学科試験
マークシート形式の4肢択一問題であり配点が80点で、そのうちの6割である48点以上をとれば合格です。
ただし、基礎科目群・専門科目群別のいずれかにおいて、正答率が30パーセント未満であった場合、全体の点数が48点を超えていても不合格となります。
実技試験
配点は3科目、30点満点で合計が90点です。
これも学科試験と同じで、6割以上(54点以上)をとれば合格となります。
ただし、学科試験と実技試験、両方において合格点をマークしなければ資格取得とはなりません。
(例:学科試験80点で実技試験53点→不合格)
とはいっても、歯科技工士の資格試験合格率は非常に高く、令和6年度国家試験合格率は「93.3%」とされています。
これはほかの医療系国家資格と比較しても非常に高い値です。
出典:厚生労働省「令和5年度歯科技工士国家試験の合格発表について」
https://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/successlist/2024/siken22/about.html
歯科技工士の実技試験は3つの項目がある
ここからは、「実技試験」の内容や勉強方法について見ていきましょう。
歯科技工士の実技試験は、下記の3つからなります。
・石膏棒 彫刻
・ワイヤー屈曲
・歯の外形描記またはデッサン
すべて歯科技工士として働くうえで必要不可欠なスキルであり、試験ではそのスキルが備わっているかどうかを見られます。
石膏棒 彫刻
歯科技工士はその仕事において、石膏という材料を扱います。
石膏を使って模型を作り、患者様の歯に合わせた詰め物や、かぶせ物などを作っていきます。
また、上下14種類の歯の形態や特徴を覚えるために『歯の解剖学 実習』という授業の中で石膏棒の彫刻トレーニングを行います。
そのため、実技試験においても、この「石膏棒を使った歯の彫刻技術」が問われます。
1本の歯を石膏棒で彫刻する課題が出されるため、彫刻の腕はもちろんのこと、歯そのものに対する深い理解力が求められます。
ワイヤー屈曲
ワイヤー屈曲では、ワイヤーの屈曲技術を問う問題が出されます。
ワイヤーは矯正器具の代表的な素材であり、これを適切に曲げられるかどうかで問われます。
扱うワイヤーの太さは試験によって異なりますが、プライヤー(ワイヤーを曲げるための器具)と自分の指を使ってワイヤーを曲げていくもので、個人の手先の動きや練習した成果などが試験結果に反映されやすい項目だといえます。
歯の外形描記
「デッサン」とも呼ばれます。
これは、試験当日に「指定された歯に対して、さまざまな角度からそのかたちをデッサンしなさい」などの問題が出されるという課題です。
たとえば、「上顎の右側第一小臼歯を、頬側の面/かみ合わせの面/舌側の面から描記せよ」という課題が出されます。
どこの歯が指定されるかは、当然課題が出されるまで分かりません。
そのためこれも「彫刻」と同じく、すべての歯の形状を把握していることが大前提になる科目だといえるでしょう。
もっともここで述べた「試験範囲」は、あくまで過去の資格試験の出題傾向を踏まえたものです。
歯科技工士の資格試験は「毎年、まったく同じもの・同じ課題が出される」というものではありません。
そのため過去問を踏まえつつも、総合的な知識をつけることが求められます。
歯科技工士の実技試験突破に必要なもの
歯科技工士の資格は合格率が非常に高いものですが、それでも不安を抱える人は当然いるでしょう。
ここでは、歯科技工士の実技試験突破のために必要なものをご紹介します。
実技を支える「知識と座学」
歯科技工士の実技試験は、単純に「手先の器用さ」だけを問うものではありません。
上でも述べたように、特にデザインの課題などは、「すべての歯に対して、包括的な知識をもっていなければ突破が難しいもの」です。
そのため、実技試験にいたるまでに、しっかり座学で知識をつけていくことが大切です。
座学で身につけた知識は、学科試験だけではなく、実技試験にも生かされるでしょう。
実技試験の練習
知識をしっかりつけていくことと同様に重要なのが、「実技試験の練習」です。
実際に、石膏やワイヤーなどを使って実技試験(および実際の仕事)の練習をしていくこともまた、試験の突破において非常に重要です。
なおこのときには、「時間内に仕上げること」も求められます。
歯科技工士の実技試験は当然時間制限が2時間で3科目あるため、「定められた時間内で、求められるクオリティのものを仕上げる時間管理の能力」も身につけていくことになります。
しっかりしたカリキュラムと指導者
まったく未知の分野に飛び込もうとする人たちを導き、国家資格試験の突破に繋げるためには、しっかりしたカリキュラムが組まれた養成校を選び、その指導者の元で学ぶことが重要です。
歯科技工士は、専門の養成機関(専門学校の2年制または3年制・大学4年制)で指導を受けることが義務付けられている為、養成機関選びはしっかりと時間をかけて行う必要があるでしょう。
オープンキャンパスへの参加も検討しよう
「歯科技工士になりたい」と考えている人は、一度オーブンキャンパスへの参加を検討してみるのもよいでしょう。
オープンキャンパスの内容は学校によってプランや実習など内容が異なりますが、その学校で実際に学んでいる先輩方の姿を見ることができますし、仕事で実際に使う道具を使った歯科技工物を作ったりすることができます。
(なお東洋医療専門学校の歯科技工士学科の2月のオープンキャンパスでは、人工歯を並べて部分入れ歯作りや、レジンチャーム作りを行いました)
まとめ
歯の健康を守る仕事である歯科技工士は、養成校での修練期間を経たのち、学科試験と実技試験から成る国家資格試験を突破して初めて就ける仕事です。
なお歯科技工士の実施試験は、「彫刻・ワイヤー屈曲・デッサン」の3つの項目があります。
歯科技工士の資格試験を突破するためには、知識をつけるための座学、実際に手を動かして彫刻やワイヤー屈曲などを行う経験、しっかりしたカリキュラムが組まれた養成機関と指導陣が必要です。
東洋医療専門学校ではこれらすべてを網羅する歯科技工士学科を運営しています。歯科技工士になりたい人は、22年連続国家試験合格率100%はもちろんのこと、満足度が高い就職先を必ず斡旋できる東洋医療専門学校・歯科技工士学科にぜひお越しください。