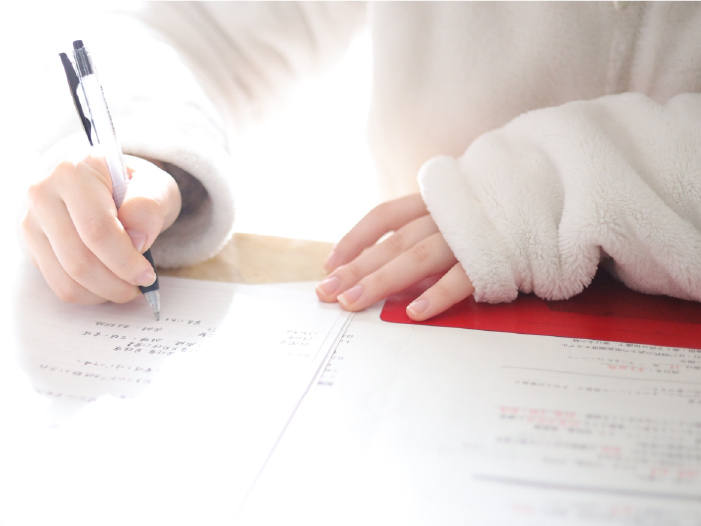Toyo Medical College
柔道整復師に向いてる人はどんな人?適正タイプや求められる人物像

柔道整復師は、定年がなく一生かけて続けられる魅力的な仕事です。
今回は
・柔道整復師とはどんな仕事か
・柔道整復師に向いてる人はどんな人か
について解説していきます。
柔道整復師とは、打撲や捻挫などの身近なけがに寄り添う仕事です
柔道整復師とは、人の健康を守ることを生業とする職業の一種です。
交通事故で発生するむちうちや、スポーツ時に起きた骨折や打撲、捻挫など、骨や筋肉のけがに対してアプローチをすることができます。
また、整形外科などリハビリテーションの現場で、理学療法士や作業療法士とともに活躍することもできます。
また柔道整復師は国家資格です。
柔道整復師になるための勉強は通信教育だけで完了することはできず、必ず専門の養育機関(専門学校・大学)で学ばなければなりません。
国家試験というハードルをクリアしなければなりませんが、高い専門知識・技術を有しているという証明になりますので、非国家資格である整体師などとは明確に区別されます。
求人も非常に多く今後も高い需要が見込まれる仕事であるため、柔道整復師の資格を取得することは、就職活動においての大きな武器になるはずです。
では、どのような人が柔道整復師に向いてるのでしょうか。
こんな資質を持つ人は、柔道整復師にぴったりです

一概に「こんな人は柔道整復師にはなれない」「こんな人は絶対に柔道整復師になれる」と言い切ることはできません。
ただそれでも「柔道整復師に向いてる人」はいます。それは、以下のような人です。
1.人とコミュニケーションをとることが好きな人
2.器用な人
3.謙虚で、自己研鑽を怠らない人
4.「新しい時代の技術」「新しい時代の不調」を勉強していける人
5.自分自身もスポーツをしていた人
ひとつずつ見ていきましょう。
1.人とコミュニケーションをとることが好きな人
ほかの医療系・介護系・リハビリテーション系の仕事についても同じことがいえますが、柔道整復師もまた、「人とのコミュニケーションが必須となる仕事」であるといえます。
患者さまの症状や困っていることを聞き出すのはもちろん、なぜそのような状況に陥ったのかの背景を聞き出したり、これから気を付けるべきことを伝えたり、治療の方針を分かりやすく示したり、といったコミュニケーションが必要になります。
そのため、人とコミュニケーションを取ることが上手く、また相手に分かりやすい言葉で伝えられるだけの技術を持っている人が望ましいといえるでしょう。
勉強をしていくうち、あるいは実際の実務をこなしていくうちに勉強できる部分もありますが、今までの生活の中で幅広い年代の人と付き合い会話を交わしてきた経験が豊富な人はアドバンテージがあると考えられます。
なぜなら柔道整復師の活躍の場所となる整骨院には、スポーツでけがをしたお子さんから交通事故で首を痛めてしまった中高年の方、また膝を痛めやすくなったご年配の方など、多くの年代の方が足を運んでくるからです。
柔道整復師の学校には夜間部のある学校がありますが、夜間部に進学して幅広い年代の方と接することは柔道整復師として活躍する上で求められるコミュニケーション力をより養える環境であるといえます。
2.器用な人
柔道整復師は基本的には「自分の手」で患者さまと向かい合うことが多い仕事であるともいえます。
そのため、手先が器用な人は柔道整復師として活躍しやすいでしょう。
たとえば「ギブスや包帯での固定」「テーピング」などは、ある程度の器用さが求められる仕事です。
また、上でも述べたように、整骨院などに訪れる患者さまは年齢も性別も体格も運動機能もさまざまです。
柔道整復師はそのような患者様お一人おひとりに対して、最適な処置をしなければなりません。
そのため、どんな年齢・性別・体格・運動機能の人に対しても、きちんと的確なアプローチができるだけの技術が必要です。
ちなみに柔道整復師の場合は、自分の手を使って患者さまの骨や筋肉の状態をはかることもあります。
そのため、手先の器用さはもちろん、手指の敏感さも求められます。
もちろん初めから全て上手にできる方はいませんし、不器用だから柔道整復師になれないということはありません。
そういった技術を身につける為に学校があります。
器用さに不安を感じる方は実技の授業を豊富に行っている学校を選択すると良いかもしれません。
3.謙虚で、自己研鑽を怠らない人
柔道整復師は、「先生」と呼ばれる機会が非常に多い仕事です。
早い人ならば21歳で資格を取得し、現場に出ていくことになります。
このような段階で「先生」と呼ばれるようになると、自分自身でも意識しないうちに、つい謙虚ですなおな気持ちを失ってしまう可能性もあります。
結果として、患者さまの言葉や要望、訴えに耳を傾けず「自分が良いと思っている治療方法」を相手に押し付けてしまったり、患者さまに対しての心配りを忘れた対応をしてしまったりする人もいるかもしれません。
柔道整復師として仕事をしていくうえでは、常に謙虚な気持ちを持つことが大切です。
また自己研鑽を怠らず、常に自分を磨き、向上心を持てる人はどんどん成長していくことができるでしょう。
もちろん、国家資格を持つプロとして、自分の技術や知識、施術に自信を持つことは重要です。
ただそのなかでも謙虚さを失わず、常に高い意識を持てる人は柔道整復師に向いてるといえます。
4.「新しい時代の技術」「新しい時代の不調」を勉強していける人
柔道整復師になるためには国家資格試験を突破する必要があります。
そのため、養成機関に入った人はまずはこの国家資格試験を突破するための勉強をしていくことになります。
しかし「現在使われている知識や技術や資器材」も「現在教科書などで取り扱われている『不調』」も、不変のものではありません。
医療は日々進歩していっていますし、また人が訴える不調も時代とともに変わっていくものです。
柔道整復師は「資格を取れば、それでもう勉強をしなくてもよくなる仕事」ではありません。
現場に出てからも、日々移り変わる技術や人の訴える不調を学び、それに対応していくだけの勉強が求められます。
5.自分自身もスポーツをしていた人
必須ではありませんが、自分自身もスポーツをしていた人は柔道整復師に向いてるといえます。
整骨院に来院する患者さんの中には、スポーツでケガをしたという方も多くいます。
このようなとき、「自分自身もまたスポーツをやっていた」という経験は大きな意味を持つことになるでしょう。
そのけがを自分自身もしたことがある……という場合は対処方法も分かりやすいものですし、たとえそうでなくても「スポーツをやりたいのにできない患者さまの気持ち」によりしっかりと寄り添うことができます。
なお「柔道整復師」という名称ではありますが、当然その仕事の範囲は柔道で起きたけがに限るわけではありません。
柔道整復師として働くうえで知っておきたいこと
ここでは「柔道整復師に向いてる人の特徴」について解説してきました。
もっともここで挙げた5つの要素に当てはまることがない人であっても、「自分は柔道整復師になれないんだ…」と考える必要はありません。
コミュニケーション力も柔道整復師としての技術や知識も、学校で学ぶうちに身に付けていくことができます。
柔道整復師になるために何よりも重要なのは、「だれかの助けになりたい」という気持ちなのです。
このような気持ちを持っている方は東洋医療専門学校で一緒に学びませんか?
イチからスタートするアナタがプロの柔道整復師になれるよう、全力でサポートします。